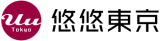あきはばら
秋葉原
東京の東西・南北の交差点、秋葉原といえば「電気街」「IT部品技術街」「アニメの聖地」「ゲームの聖地」「メイドカフェ」「サブカルチャー」「カプセルトイ」などの人気が重なる街として知られています。
その起源は江戸時代、一夜にして町全体がなくるような大火が多発していました。当時の江戸っ子は、秋葉権現様(現在の静岡県の)が火伏せ(火除け)に効果があると信じていました。そこで幕府は鎮火神社を神田の空き地に建てます。これを「秋葉様」、「秋葉さん」と呼んだと言います。その後、別地に秋葉神社として移転されたため、空地=原っぱの意味で「アキバっぱら」と呼ばれ、鉄道が通った時に「秋葉原」の駅名としました。
秋葉原の発展について

秋葉原の発展は、隅田川の支川の神田川の開削により、木材料や生活物資を江戸の奥地に運ぶ拠点となったことです(木材置き場)。地の利は良く、現在では、山手線/京浜東北線、総武線が交差する要所で、皇居・大手町はもちろん、日本橋・神田の五街道の起点であり、本郷・上野の神社仏閣参拝の通り道であり、隅田川・両国の海上運搬ルートなど、人も物資も通過する街です。
秋葉原電気街

ラジオ・TV部品、家電、無線、IT、パソコン、ネットワーク、携帯端末の部品など「何でも揃う部品の街」として有名です。

秋葉原ラジオ会館

カードゲーム、フィギュア、キャラクターグッズなどの専門店が揃っています。
入徳門(湯島聖堂)

五代将軍徳川綱吉が儒学振興のために建てた塾(正しくは儒学家林羅山の塾を上野から移転)で、湯島聖堂と呼ばれた孔子廟(孔子の学問=儒学を学ぶ場所)です。

神田川(万世橋からの眺望)